- HOME
- 大学案内
- 沿革・歴史
- 創基150周年記念
- JOYAMA通信150周年特別号
- 同窓会長インタビュー
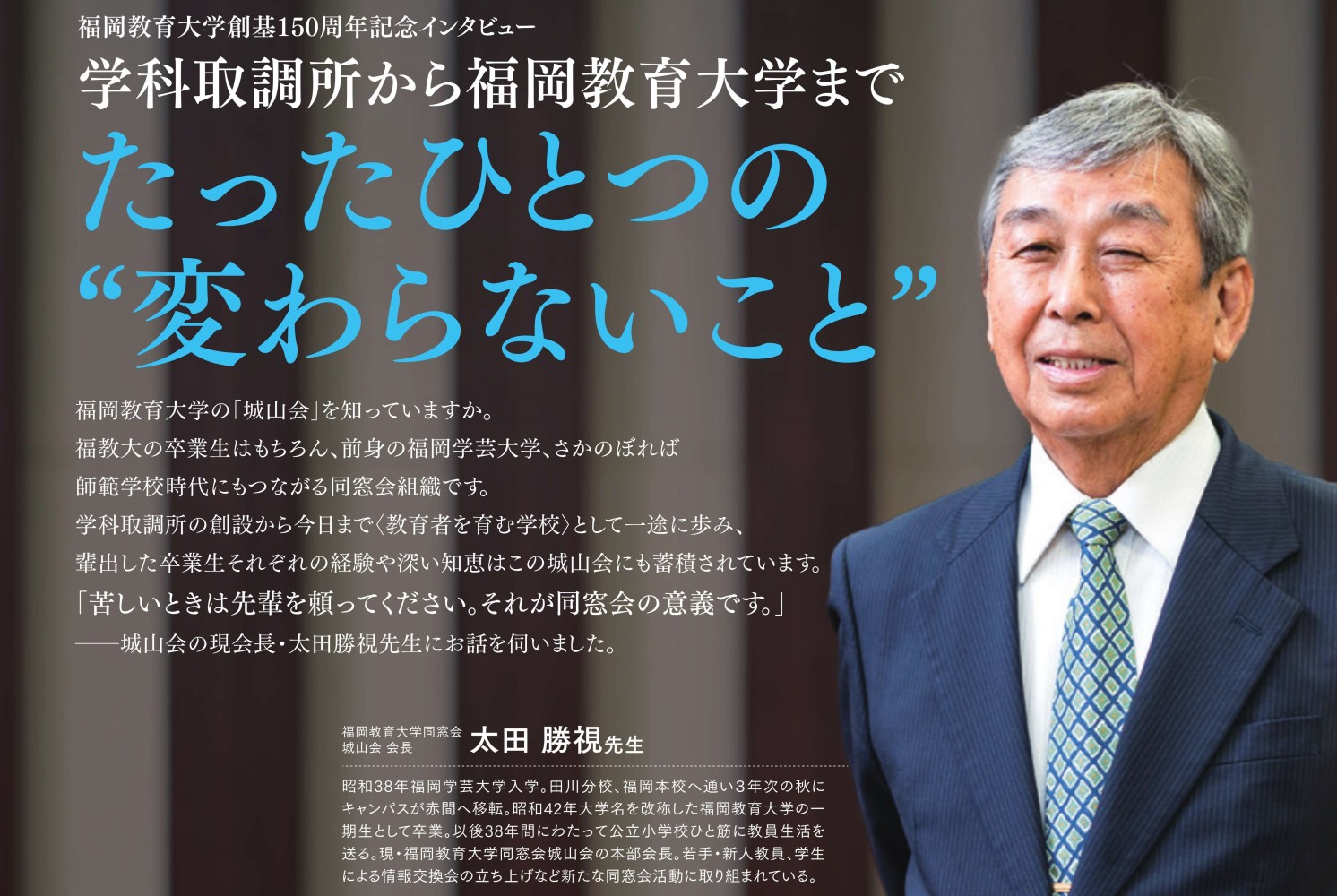
田川分校、福岡本校、赤間の3キャンパスへ通学
—太田先生は福岡学芸大学が福岡教育大学に改称する移行期に大学に在籍されていたそうですが、当時のことを伺えますか?
太田先生 私が入学した昭和38(1963)年当時、福岡学芸大学は福岡・小倉・田川・久留米の4カ所の分校に分かれていました。私は地元が田川で専攻する理科の研究室もあったので田川分校に通いました。
当時は1~2年次は分校に通い、3年になると各分校から福岡市(南区塩原)の本校に移る、という流れだったんです。自分もそうなると思っていたのですが、3年次に本校へ移った半年後、同じ年の秋には赤間キャンパスへ移ることになりました。
—資料に「本校の赤間移転は昭和41年」と記載があるのですが、その前年(昭40)から移動は始まっていたのですね。
太田先生 一部先行だったのかもしれませんね。私は田舎育ちで福岡に憧れがあって「3年になったら福岡で暮らせる!」と楽しみにしていたんですが、たった半年で赤間に移ったのでよく覚えています(笑)。4年生の先輩方も同じ時期に本校から赤間へ移ったと記憶しています。
そして、翌年3月に先輩方が卒業されて、4月に大学名が福岡学芸大学から福岡教育大学に改称されました。ですから私たちの期が福岡教育大学の名称としては最初の卒業生になります。
—分校、本校、赤間の3カ所を経験された世代は稀ですね。特に印象に残っているキャンパスはありますか?
太田先生 それぞれ思い出深いですが、やはり1~2年次の分校時代が印象に濃いです。いわゆる教養課程ですが、分校なので学生の数も少なくて家族的な雰囲気でした。なかでも所属していた小学校の理科の研究室は同級生が女子4人、男子2人と小規模で。そこに生物、物理、地学…とそれぞれの先生方がついてご指導くださるので関係性が非常に近しく、何より実習がユニークでした。
—どんな実習だったのですか?
太田先生 例えば生物の先生は私たちを連れて英彦山(ひこさん)に登るんです。自生している植物を実際に見て、葉っぱなどを採取しながら特徴を覚えるわけですね。その時々でルートを変えて皆で何度も登りました。試験になると先生がパッと葉っぱを出されて、それが何の植物でどんな特徴かを当てなければいけないんです。
—面白そう!フィールドワークが活発だったのですね。
太田先生 物理の先生がウソ発見器を作ったこともありました。いわば手から出る汗を感知する装置なんですが僕らが試すと反応するんですよ、嘘を言うと分かるんです。そういうものを先生は簡単に作られていましたね。地学の先生とは福井県の白山(はくさん)まで行きました。石を採取するんですが、砕いていくと中から化石が出てくるんです。普段は座学が中心でしたが、時にこういう指導を交えてくださって楽しみながら学んだから鮮明に覚えているんでしょうね。
—分校時代を“家族的な雰囲気”とおっしゃる意味がよく分かりました。当時、教育実習はどのように行われていたのでしょうか?
太田先生 4年間で2度行ったと思います。最初の実習は付属小学校に行くのですが、福岡や小倉と違って田川には付属小学校がないので代用付属というかたちで市立小学校にお世話になりました。2回目は公立の小学校・中学校ですが、私はどちらも母校ではなく受け入れ先を自分で探してお願いしました。
—教育実習で印象に残っていることはありますか?
太田先生 1回目の実習の時、実習生の誰か1人が全体研究授業をするのですが、断りきれず私が担当することになり非常に苦労したのを覚えています。先生にもご指導いただいて自分なりに懸命に取り組んだのですが、いざ協議会で発表すると厳しい指摘を山ほど受けました。実力不足だったのでしょう、ミスも多く涙も流しました。
でも、苦労したことほど時間が経つと思い出になるものですよね。この時に親身になってご指導いただいた先生とも同窓会の会長になって再会できました。かつては指導教員と学生の関係だった私たちが、教員同士の大先輩と後輩という関係になって。懐かしくお話ができるのも、あの時の苦労があったおかげだと思いました。
電気のない離島で複式学級を担当した新人時代
—今のお話にあった同窓会ですが、太田先生が会長を務める「城山会」は「福岡教育大学」の同窓会ですよね?
太田先生 名前で区切るとそうですが、実際のところ同窓会は福岡教育大学、福岡学芸大学、さらに言うなら師範学校も全てつながっているんです。創基150周年といわれるように、明治6年(1873)に学科取調所と呼ばれる教員養成機関が創設されて今日の福岡教育大学に至るまで様々なことが変わりましたが、ただひとつ変わらないのは常に「教育者を育む学校であった」ということです。ですから私も同窓会を通してたくさんの教員の先輩方に出会うことができました。
—同窓会は世代を超えて先輩・後輩をつなぐ交流の場、しかもOBの多くが同じ教職というのは教育大学ならでは強みですね。
太田先生 昔は職場の先輩を頼りやすかったんです。教えてもらったり助けてもらいながら気軽に関係を築けましたが、今はいろいろ厳しい部分もあると聞きます。とはいえ、悩みを打ち明けられる存在は必要でしょうし、それが同じ教員ならいっそう心強いのではないでしょうか。城山会が拠りどころになって、つながりを育む役割ができないかと考えています。若い方々は組織に入るのに抵抗があると思いますが、「採用されて1年足らずで教員を辞めた。」と耳にするたび心苦しくなるんです。親身になって話を聞いてくれる教員仲間がいたら、ひょっとしたら解決できたこともあったかもしれないと。
—太田先生ご自身も、新人教員の頃に今の時代では考えられないようなご苦労を経験されたとか?
太田先生 教員になって初めての赴任先が離島だったんです。私が就職した時代は炭鉱の閉山が相次いでいて、子どもが減った筑豊地方の教員が余っていました。その先生方が人口の多い福岡市に広域配転されて、押し出されるように新人の枠が激減して。数年間、関西や関東に行くケースも多く、私も福岡市に合格したものの全国どこに赴任するか全く分からない状況でした。そんな中で打診されたのが、住所こそ福岡市ですが本島から約40kmの沖合にある小呂島(おろのしま)でした。行くか行かないかは選んでいいのですが「どこでも行きます!」と即決して。ですが、その時の私は何もイメージできていなかったんです。姪浜(福岡市西区)の港から小さな4トン漁船で約4時間。頭上から落ちてくるような高波の中で甲板にしがみついて、やっとの思いで到着した島には電気も十分な水もなく。本当に驚きの連続でした(笑)。
—昭和40年代に電気が通っていなかったんですか!?
太田先生 自家発電だけでした。だから電気が使えるのは夜の3時間くらいで、あとはランプです。島には井戸がひとつしかなかったので水も貴重でした。男性教員は校内に部屋を割り振られて、夕食は用務員室に集まって皆で食べて。生活の全てが学校の中にありました。
—子どもたちや授業はどんな様子だったのですか?
太田先生 複式学級で私は3・4年生を担当しました。児童は2学年あわせて7人。当時はまだ複式教科書がなく、2学年分の教科書をまとめて渡されましたが、一般的なクラス担任もしたことがない新人が教えられるわけがないですよね。でも当時はそんなこと考えもせず、「この7人にどう理解してもらうか」と必死に知恵を絞るわけです。はじめは3年生を前の黒板、4年生は後ろの黒板を使って別々に教えていましたが、それでは教科書が到底終わらない。最終的には先生方のアドバイスも受けながら、3・4年生の理科を2年間で一緒に学べるカリキュラムを自分で作りました。
友人に会えない、出掛けるお店もない生活はきつかったですが、あの時代の経験が教員としての原点になったように思います。「ひとりも落としたらいけない」ことを胸に刻んだのもあの時代でした。
—離島の次はどちらに赴任されたのですか?
太田先生 西新小学校(福岡市早良区)でした。今度は一転して街中の学校で1学年が4~5学級、1クラス40人の規模でした。島とは何もかもが違って、また新人のような気持ちで取り組んだのを覚えています。教え方はまだ下手でしたが子どもたちと一緒になって勉強して、授業が終われば運動場でドッジボールして。クラス全員と交換日記もしました。提出の強制はせずに、一人ひとりと向き合って子どもの夢に近づいて、私の想いも語って。「あぁ、やっぱり先生という仕事はいいなぁ」と思う瞬間を何度も経験させてもらいました。当時担任したクラスは今も毎年、同窓会を開いてくれるんですよ。11歳、12歳だった子どもたちも年齢を重ねて見た目がもう私と変わらない、どちらが先生か分からないみたいになって(笑)。これが教員冥利です。
新人・若手教員、学生をつなぐ若手だけの情報交換会
—学びも遊びも共にして「子どもと一緒に成長し続ける先生」を目指す学生さんは今も多いと思います。
太田先生 時代も変わって今の先生や学生さんは、私たちの時代とはまた違った大変さも多いと思います。難しい時代にあっても挑戦する気持ちを大切にしてほしいですし、それから同級生でも先輩でもいい、自分が尊敬できる人と出会ってほしいと願っています。
—福教大生には城山会もありますものね。大学の同窓会というと「大先輩が主役の会合」というイメージもありましたが、太田先生が会長に就任されて若手を対象にした取り組みも始まっていますよね?
太田先生 その年に採用された新人教員と、教員になって1~2年くらいの若手教員の情報交換会を数年前に立ち上げました。大学に集まってお互いの苦労話や相談事を共有する会ですが、今後は現役の福教大生もたくさん参加していただき「学生・新規採用者・若手教員の情報交換会」のかたちで年1回実施する予定です。悩みや現場の情報、学生が採用試験の相談をしてもいい、運営しながら方向性もかたまっていくでしょう。
福岡県内、他県内の各地域には28の同窓会支会、6の支部があり、こちらも様々な研修会を行っています。参加は単発でも構いません。いろいろな方と知り合い、つながる場として城山会を使っていただきたいです。そして、苦しいこと、困ったことがあるときは先輩を頼ってくださいとお伝えしたいです。それが「教育者を育む学校」で受け継がれてきた同窓会の存在意義だと私は思っています。
—太田先生、貴重なお話をありがとうございました!

