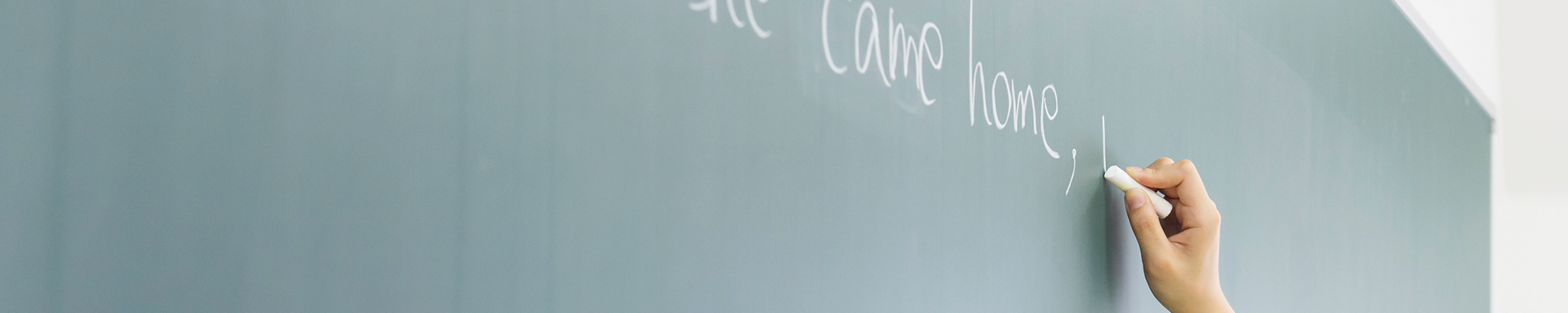令和5年度 優秀教育実習生賞 受賞
学校の主役は子どもたち。教師は理解者でありサポーター。
初等教育教員養成課程
北川 楓弥さん
KITAGAWA FUYA
現場でしか学べないICT教育の実践や、教師の仕事の本質。

一年次の体験実習では、小学校の現状について知ることができ、新しい世界に触れることができました。まず授業一つとっても、私が小学生の頃とはまったく違います。児童一人ひとりがタブレットを使っていたり、教師が電子黒板やICTを積極的に取り入れていたり、情報通信技術を学校全体に取り入れていることを実感しました。大学の講義でもICTの活用について学んでいましたが、実際に学校現場でどのように実践されているのかを体感することができました。また、授業以外での児童との接し方、運動会などの催しにおける教師の役割、給食・掃除指導など、自分が全く知らなかった学校現場での教師側の取り組みについても知ることができ、学校現場でしか学べないことが多くありました。
そして二年次での基礎実習では、実際にどのように授業の中で児童にアプローチしていくべきなのかを学びました。特に観察参加で先輩方の授業を拝見し、翌年の本実習が楽しみになったことを覚えています。同時に、先輩たちと自分を比べて自身の未熟さも痛感し、来年までにさまざまなことを吸収して成長したいと強く思うようになりました。
楽しく活発に学びを深めてもらうため。授業は本番だけでなく準備も大切。

体験実習や観察参加を通して印象に残っているのは、教師と子どもたちが授業中にとても楽しく活発に学びを深めていた姿です。私もこのような授業がしたいと思い、授業の進め方、児童との接し方、授業中の立ち回り方など全てにおいて自分の将来を想像し、本実習に臨みました。そして迎えた三年次の教育実習はとても楽しく、充実した3週間でした。
私は社会科が査定授業でしたが、児童がより興味・関心を持つことができるように、全国的な資料が載っている教科書だけでなく、学校周辺の情報も集めて授業を行いました。おかげで児童が「ここは〇〇だ!」と自分が知っている場所が出るたびに目を輝かせて授業に入り込み、積極的に取り組んでくれました。授業準備で、その単元に関わる身近な資料を集めることは大変でしたが、そんな地道な準備こそ、より良い授業を作っていくために必要なことだと実感しました。どのように授業を進めるのか、板書はどのようにするのか、授業の前にどれだけ教師が児童を想定して授業準備をできるか。これは社会科だけでなく、どの教科にも言える大事なことだと思います。
子どもたちとの信頼関係を大切に、一番のサポーターでありたい。
私は三年間の実習を通して、子どもたちが目を輝かせながら学習に取り組んだり、運動会などの行事に本気になって練習したりしている姿を見てきました。その中で、教師にとって子どもたちとの関わりがいかに大切であるかを学びました。教師と子どもの信頼関係を築くためには、朝休みや休み時間での遊び、行事等のサポート、給食・掃除指導などの生徒指導等、授業中以外の時間での子どもたちとの触れ合いが大切です。
私が目指すのは、子どもたちが主体的に学びを深めることができるようにサポートできる教師です。学級運営の主役は教師ではありません。教師が主体となるのではなく、あくまでも子どもたちのサポートをしながら、一体となって学級を作っていきたいです。そのために、教師として、子どもたちの知的好奇心を奪わずに、日常生活からより良い学びが得られる環境を作りたいと思います。子どもたちとの信頼関係を大事にしながら、子どもたちが学びを深めることができる1番の理解者、サポーターとなれるような教師を目指します。