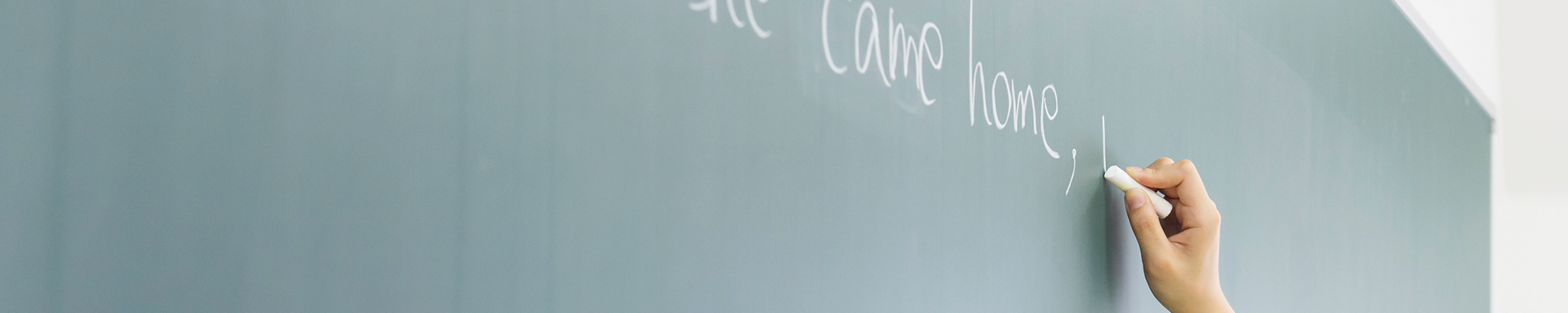令和4年度 優秀教育実習生賞 受賞
「なぜ」と問いかけ続ける。生徒にも、自分自身にも。
特別支援教育教員養成課程
藤本 颯真さん
FUJIMOTO SOUMA
すべての実習に、新しい気付きと学びがある。

教育学部では、1年次の体験実習、2年次の基礎実習と観察参加、そして3年次の本実習と段階的に実習を行います。いずれも生徒や先生方から多くのことを学んだ貴重な経験でした。
体験学習は、基本的には先生方が行う授業の補助として参加させていただくのですが、生徒一人ひとりの特徴や学級全体の様子を観察し、生徒同士が助け合おうとしていたこと、クラスメートや先生のアドバイスを素直に聞く様子などが印象に残りました。また先生方が生徒一人ひとりの実態に配慮した指導を行っていく姿を見て、叱り方や褒め方などを学ぶことができました。特に生徒が取り組みに成功したり、失敗したりした際に「なぜ」という問いかけを行って、良かったことはまたできるように、同じ失敗を繰り返さないようにする指導がとても参考になりました。
また模擬授業を行う基礎実習では、他の学生の模擬授業を見学して、実際に附属学校の先生の話を伺うことで、自分自身の模擬授業の質をより高め、3年次の本実習に向けて備えることができました。
指文字や筆談で積極的に交流してくれた、特別支援学校の生徒たち。

本実習の授業では先生のアドバイスをもとに、自分が説明するだけでなく、生徒が考え、それを共有させるように授業を作ることを心がけました。時間配分に苦労しましたが、生徒からわかりやすかった、楽しかったという言葉をもらえた時は、本当に嬉しかったです。作成した授業プリントに、生徒が熱心に記入してくれていたことにも感動しました。
また、特別支援学校での実習では、授業で使うスライドの背景を黒にすることや、授業をする際に立つ場所を変えることなどに工夫をして、できる限り生徒が授業の内容に集中できるように気をつけました。もっとも工夫したのは、言葉の使い方です。わかりやすい表現をしないと伝わらない可能性もありますが、一方で、表現が簡単すぎると生徒の学びにつながらない可能性もあり、そのバランスを考えるのが大変でした。
特別支援学校ならではの苦労もありましたが、同時に嬉しいことも多くありました。私が手話でわからない単語があったときに生徒の皆さんが教えてくれたことや、手話が伝わらない時は指文字や筆談などでたくさん会話をしてくれたことはとても嬉しかったです。
生徒とのコミュニケーションは、教員のやりがいだと思う。
私は実習を通して、中学校であっても特別支援学校であっても生徒一人ひとりをしっかりと観察することが大切だと学びました。生徒の特徴を把握することで、生徒全員が参加できる授業、学級を作っていくこと。そのためには、生徒と教員との間に信頼関係を築くことが大切です。生徒が授業に一生懸命に取り組んでくれる姿や日々生徒とコミュニケーションをとる時間が、教員にとって大きなやりがいを与えてくれるのだと思いました。
また、実習中には指導担当の先生に授業の改善点を指摘していただき、それを修正することにも、大変ではありましたが、それと同時に楽しさとやりがいを感じることができました。生徒に対してだけでなく、自分自身にも「なぜ」と問いかけて、それを修正することは重要だということを学びました。
私が目指すのは、まず一番に生徒を中心に考えることができる教師です。そのために周りの方々の支えがあるということを忘れず、生徒一人ひとりを理解し、感謝の気持ちと謙虚な姿勢、生徒を想う気持ちを忘れない教員になりたいと思います。