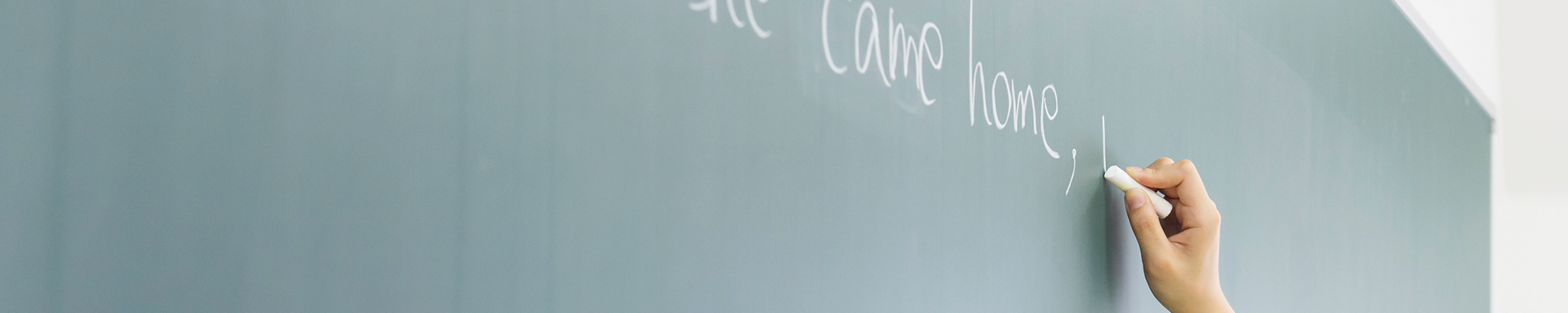令和4年度 優秀教育実習生賞 受賞
「芯のある教育」で、目の前の子どもを見つめる
初等教育教員養成課程 幼児教育選修
青木 みのりさん
AOKI MINORI
同じ場所で同じ子どもと接しても、気づく視点はそれぞれ。

体験実習では、保育参観・補助を行いました。その後、クラスで体験実習を通して感じたことや気付いたことを発表したのですが、同じ場所で、同じ子どもたちと関わる実習を行っていても、全く異なる点に気付いていた人がいて、少人数のグループでも様々な意見があがりました。幼児教育の世界に飛び込んだばかりの1年次は、視点を多くもちながら保育を学んでいくことの大切さを知りました。また、自分自身の課題も多く見つかり、子どもと関わる経験を積んでいくことや、遊びや教材の研究を深めることを、今後の目標としたいと強く感じました。
2年次の基礎実習では、幼稚園の先生方から、保育指導案の作成の仕方や、園の年間計画をもとにした保育や遊びの展開についてなど、様々なことをご指導いただき、2年間での学びを実践と少しずつ結びつけ始めた時期でした。
本実習を行う先輩たちの動画を見て「1年後、自分も同じようにできるだろうか」と不安になる部分もありましたが、それ以上に、子どもたちの様子や、互いに高め合う実習生の姿、真摯に向き合ってくださる幼稚園の先生方の姿に、幼児と触れ合うことへの楽しみと意欲が増し、本実習への期待が膨らみました。
運動会に向けてがんばる園児や、元気な小学1年生との触れ合い。

幼稚園での本実習は、運動会期間であったため、そこに向けた活動を行いながら、子どもたちの楽しみな気持ちや意欲が高まっていくように工夫しました。本番に向けて活動する幼児の姿を間近で見ていくと、3週間という期間でも、一人ひとりの成長した姿や、クラスの力の深まりを感じ取ることができ、とても嬉しく、大きなやりがいを感じました。
続く小学校の実習では、1年生の生活科を担当し、写真や映像を活用したりするなど、子どもたちの「したい」という気持ちを大切に、活動を展開していくことを意識していました。また、幼稚園実習で安全な環境づくりに関して課題が見つかったため、小学校での生活科の授業では、児童が安全に、心から楽しんで活動することができるような場を考えながら、様々な用具を使って場づくりを工夫していきました。幼稚園より多い35人の児童がいる中で教師の声が通らなかったり、活動の時間を切り上げることができなかったりと、場をまとめるのは大変でしたが、有意義な小学校実習となりました。35人というたくさんの児童と触れ合えるからこそ、嬉しい場面や楽しいやり取りもたくさんあり、学びと喜びの多い2週間であったと感じています。
学校全体が一つのチーム。一貫性をもって子どもたちのために!
3年次までの実習を通して、大学で学ぶ理論と実践との違いを痛感したと同時に、常にシミュレーションを行うことが重要だと学びました。いざ子どもたちを目の前にすると、緊張から思い通りに動けないことも実習では多くあります。だからこそ、大学の講義で知識を増やしていくことはもちろん、ボランティアなどの様々な機会で、子どもと直接触れ合う経験を積み重ねておくことも重要です。
また、自分の考えや保育に一貫性をもつことの大切さも学びました。芯のある教育を行うためにも、保育や授業を考えたり、シミュレーションを行ったりする際には、「目の前の子どもたちに、今必要なことは何か」を1番に意識するという姿勢を磨いていきたいです。
約5週間の本実習で、子どもたちとともに私自身も成長した部分が多くあると思います。今後も、たくさんの子どもと出会う中で、教師として、一人の人間として、成長し続けていきたいです。
そしてもう一つ、本実習を通して実習生同士の、特に同じクラスに配属される仲間との絆が強まったことからも、学校において、チームの力はとても大きいのだと実感しました。先生方の連携や、組織としての結束力が感じられたことも印象的で、「チーム学校」を胸に、他者と高め合える教師となりたいと思いました。